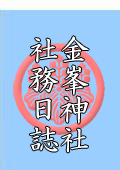天神社の例祭の後、そこから近い黒津町の春日神社の例祭へ。
市内北部の神社の中では境内も広く立派なたたずまいです。
この春日神社は金峯神社と縁が深く神社の成り立ちに大きく関わっていると伝えられています。
金峯神社と春日神社の間の道を「例幣使道」といい幅八間の直線の道がつながっていて、金峯神社の流鏑馬ではこの春日神社まで馬が駆けたと伝えられています。
流鏑馬の第二騎手が射る的を「春日の的」というのはこの春日神社から来ています。
境内には春日神社に並列し諏訪神社が祀られています。
この地域では、傍に流れる信濃川との関わりが深く、以前は「島虫様」と言ってツツガムシの被害が大きく虫除けの祭事が盛んでした。
川を渡ったり河川流域の畑や魚なども捕れたのでしょう、人々の生活と信濃川は切っても切れない関係にあり、五色の幣束を竹に差しお祀りするのですが近年では全く行われなくなりました。
これも時代の移り変わりではありますが、地域の記憶として伝えていきたいと考えます。(桃)