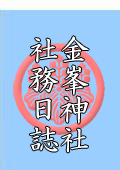今日11月23日は「勤労感謝の日」として国民の祝日に定めされております。
勤労感謝の日とはそもそも新嘗祭(にいなめさい)がその由来です。
日本人にとって五穀(米・稗・粟・麦・豆 諸説あり)の収穫は、古来より非常に大切なものでした。11月23日に天皇陛下が新穀を天神地祇にお供えをし神事を行い、その年の収穫に感謝する宮中祭祀のひとつで、日本中の神社でも祭事が執り行われています。
特に稲は単なる食べ物ではなく、日本人の主食としてまた文化の源流として深く根付いたものであり、租税の主幹として一年を養う大切な蓄えとなることから、大事な行事として飛鳥時代の皇極天皇の御代に始められたと伝えられています。
新嘗祭に合わせて、新穀を奉納いただきご神前にお供えいたしました。
我が国の食物自給率は、生産額ベースで69%、カロリーベースで39%(平成22年度農林水産省)と大変低く、今社会問題となっているTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の是非を含め、生産や輸入から消費に至るまでの食糧の料・値段・安全性の確保など大変不安を感じる問題です。また東日本大震災後の福島第一原発事故による放射能汚染の問題はどなたにとっても重要な関心事だと思います。
神社の人間にとって専門分野ではありませんが、食料の確保は天候や社会状況に大きく左右され、毎年2月の祈年祭(きねんさい としごいのまつり)で豊作を祈り、11月の新嘗祭では収穫を神様に感謝する生活が長い間の日本人の姿であり、神の恵みに深く感謝する姿勢は今の世の中にも重要な教になると思うのですが、いかがでしょうか。(桃)
/p