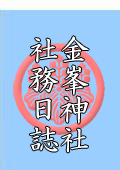6月に入り梅雨が近づいているせいか、雨の日も多くなってきました。
梅雨特有のじめじめした季節ももう間近ですね。
先月の28日(日)新開町の神明社の例祭が行われました。
件数にして10数件の氏子町内で、市内川西の北部に位置します。
公民館の裏手に神社が鎮座していますが、その向こう側はずっと水田が広がり夏でも風通しは良さそうですが、毎年早朝7時半からの祭典でこの日は特に風が強く少し肌寒い日でした。
それでもずっと広がる水田を眺めながらの祭典はとても心が落ち着くものです。日本の原風景的な眺めにすっかり癒される早朝でした。その後は慌ただしい一日でしたが・・・
雨天時には公民館の中から遥拝で祭典を行いますが、毎年晴れた日が多いです。(桃)